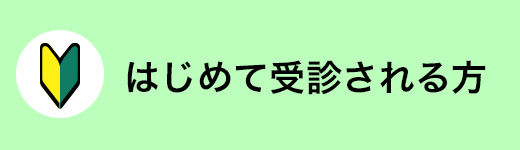気管支喘息(ぜんそく)
気管支喘息(ぜんそく)とは?
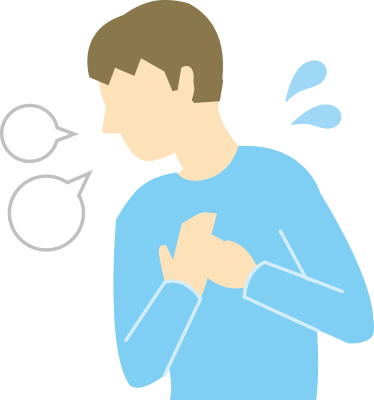
一般的にぜんそくとは気管支喘息(きかんしぜんそく)のことをさし、慢性的に気管支の粘膜が炎症をおこす病気です。何らかの刺激を受けたときに気管支が狭くなり、呼吸がしにくくなることがあり、これを「ぜんそく発作」と呼びます。発作時には咳、喘鳴(ゼーゼーやヒューヒューと音を立て息苦しくなる状態)、呼吸困難などの症状をおこします。ぜんそくの原因は様々ですが、多くは気管支におけるアレルギー反応が原因となります。その他にも、運動や薬剤が原因となって発症することがあります。
ぜんそくの症状
ぜんそくの症状は人によって様々ですが、代表的なものとして以下のようなものがあります。
- 咳: 乾いた咳や、痰を伴う咳などが特徴です。特に夜間や明け方に症状が出やすいことがあります。
- 喘鳴(ぜんめい): 呼吸をする際に、ヒューヒューやゼーゼーという音が鳴ります。
- 呼吸困難: 息苦しさを感じ、呼吸が苦しくなります。
- 胸部締め付け感: 胸が締め付けられるような感覚があります。
これらの症状は、運動や寒い空気を吸う、風邪をひく、花粉やハウスダストを吸い込むなど、様々な体の外からの刺激によって誘発されることがあります。
ぜんそくの原因
ぜんそくの原因は、遺伝的な要因と環境的な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。ぜんそくは、お子様の病気と思われる方がいますが、大人になってから発症するタイプがあることもよく知られています。
- 遺伝的な要因: 家族にぜんそくの人がいる場合、自分もぜんそくになりやすいと言われています。
- 環境的な要因:
- アレルゲン: 花粉、ハウスダスト、ペットの毛など、アレルギー反応を引き起こす物質が主な原因の一つです。
- 大気汚染: 排気ガスや大気中の粒子状物質などが気道の炎症を悪化させます。
- 感染症: 呼吸器感染症がぜんそくの発症や悪化に関わる場合があります。
- 薬剤: アスピリンや一部の鎮痛剤などが、ぜんそく発作を引き起こすことがあります。
- 運動: 激しい運動が誘発することもあります。
- ストレス: ストレスがぜんそくの発作を悪化させることがあります。
ぜんそくの病気の種類
ぜんそくには、大きく分けて以下の2つの種類があります。
- アレルギー性ぜんそく: 特定のアレルゲンが原因で起こるぜんそくで、最も多いタイプです。
- 非アレルギー性ぜんそく: アレルゲンが特定できないぜんそくで、運動誘発性ぜんそくや夜間ぜんそくなどが含まれます。
ぜんそくの診断
ぜんそくの診断は、問診・身体診察・呼吸機能検査・胸部レントゲンなどを組み合わせて行います。
- 問診: 症状が出るきっかけや時間帯、呼吸困難、ゼーゼー、ヒューヒューといった喘鳴、咳、胸の圧迫感などの症状について詳しく確認します。運動、花粉、ダニ、冷気など、症状を悪化させる原因となるものを特定するためにも重要です。
- 聴診: 呼吸の音を聞きます。とくに喘鳴が聞こえることは気道が狭くなっているサインでありとても重要です。
- 呼吸機能検査(スパイロメトリー): 肺活量や1秒量(1秒間におもいっきり吐くことのできる息の量)、フローボリュームカーブ(息を吐くスピードと量を数値化したグラフ)などを測定し、肺の働きを調べます。喘息では、気道が狭まっているため、1秒量が低下したり、フローボリュームカーブが特徴的な形になることがあります。また気管支拡張薬を使用して気道の狭さが変化するかを確認することもあります。
- 呼気NO検査: 呼気に含まれる一酸化窒素の量を測定し、気道の炎症の程度を評価します。
- 血液検査: アレルギーの原因に関する検査や、アレルギー性の炎症の程度を調べる検査を行います。
- 胸部レントゲン検査: 肺の状態を画像で確認します。
ぜんそくの治療
ぜんそくの治療は、症状の程度や原因によって異なりますが、一般的には以下の治療法が用いられます。
- 吸入療法: 吸入ステロイド薬・気管支拡張薬を吸入器を用いて直接気道に届け、気道を広げたり、炎症を抑えたりします。ぜんそくで最も重要な治療であり、当院では治療開始前に必ず、院内で吸入の練習を行なっています。
- 内服薬: 抗アレルギー薬、気管支拡張薬、ステロイド薬、などを飲み薬として服用します。
- 生物学的製剤: 重症のぜんそく患者さんに対して、免疫反応を抑える薬剤(注射薬)が使用できるようになっています。当院でも重症の患者さんに対しての生物学的製剤を使用しています。
- 生活習慣の改善: 喫煙を控える、規則正しい生活を送る、運動療法を行うなど、生活習慣を改善することも大切です。
ぜんそくと日常生活
ぜんそくの治療については、気管支の炎症を主に吸入ステロイド薬をつかってコントロールしていくことが一般的です。また、症状が悪化した際には、気管支拡張作用のある吸入をしたり、点滴や内服のステロイド薬を使用することで炎症をおさえます。症状が改善しない場合は入院をして治療することもありますが、日常生活に支障のないように、発作を起こさずに症状をコントロールしていくことが重要です。
ぜんそくは、適切な治療を行うことで、日常生活に支障なく過ごすことができます。しかし、発作を起こさないように、以下の点に注意しましょう。
- 定期的な吸入: 症状が落ち着いていても、毎日の吸入を欠かさずに行うことが重要です。
- アレルゲンの回避: アレルゲンとなる物質をできるだけ避けるようにしましょう。
- 環境の整備: 室内の湿度を適切に保ち、こまめな掃除を行いましょう。
- 規則正しい生活: 十分な睡眠をとり、ストレスを溜めないようにしましょう。
- 定期的な通院: 医師の指示に従い、定期的に受診しましょう。
まとめ
ぜんそくは、適切な治療によってコントロールすることができる病気です。当院では、診断のための呼吸機能検査や呼気NO検査をすぐに行うことができ、結果により呼吸器専門医・アレルギー専門医が患者さん一人ひとりに合った最適な治療薬を選択しています。ぜんそくの症状が気になる場合は、ぜひ当院にご相談ください。
【補足】
- 気管支: 鼻や口から吸い込んだ空気を肺に運ぶための、体のパイプのような部分です。
- 炎症: 体の一部が赤く腫れて熱を持ち、痛みを伴ったりする状態です。
- ステロイド薬: 炎症を抑える効果のある薬です。
- アレルギー: 特定の物質や刺激に対して過敏に反応し、様々な症状を引き起こす状態です。
【注意】
このページの内容は、一般的な情報であり、個々の患者さんの状態に合わせて医師が診断・治療を行うことが重要です。ご自身の症状について心配な場合は、必ず医師にご相談ください。